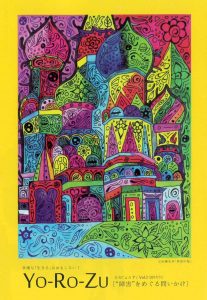[ケーキ屋だけじゃないケーキ屋]
高校二年生のときにケーキ屋になることを決心した。自分の意思ではあったけれど、そんな年齢で一生の仕事を決めることが容易ならざることだと感じられたのは、ずっと後になってからだ。
父親がケーキ職人だった。僕の性格をよく知っている母親は、ケーキ屋をやっている僕のイメージが「どうしても浮かばない」と言い、父の苦労を知っているだけに「ケーキ屋だけにはなるな」と忠告した。
卸売専門の和菓子屋の洋菓子部門に勤める父は、僕が生まれたときからほとんど家にいない状態で働いていたが、いくつかの仕事を転々とした後に、ずっと続けることができた唯一の仕事だったそうだ。
子どもの頃から父の職場に遊びに行っていた。カステラを焼く、カスタードクリームを炊き上げる、シュークリームをつくる、といったオーソドックスなケーキづくりの仕事だったが、僕をワクワクさせるものがたくさんあった。引き出しの中に入っているトッピングのお菓子に目を奪われ、職人さんが使っているクリームの絞り出し袋がサワサワとして気持ち良かった。秘密基地みたいなところで父は仕事をしているんだと思っていた。
高校時代は、そこでアルバイトを始めた。ある年のクリスマスイブ、父と職人の方と僕の五、六人で何百というケーキをつくり上げなければならなかった。その横を、数十名の和菓子職人の人たちが先に帰っていく。誰も手伝おうとしない。父も父で、「いいクリスマスにしてあげてな」と声をかけている。僕は「お先に」と帰っていく人たちに、「おかしくないですか?手伝ってもらえませんか?」と思わず言ってしまった。
そのときだった。「いらんこと言うな! 俺の世界や。お前には関係ないやろ」。父がものすごい剣幕で僕を叱った。初めて真剣に怒られた。
その日、仕事を終えて帰る道で、「俺には父親がおらんかったから、父親のやり方が分からんのや」とつぶやいた。もしかしたら、そのことで苦労したことも少なくなかったのかもしれない。そのとき僕は、この親を世界一の父親にしてやる、と誓った。
そうした経験が、僕にとっては大きな意味を持っていた。「ケーキ屋だけはやめてくれ」を押し返すくらいの。
ケーキ屋という場所が秘密基地のように映ったり、父が読んでいた洋菓子専門の雑誌で見た飴細工やデコレーションケーキの写真に「芸術性」を発見し驚いたりしたことなどもすべて含めて、僕にとっての「ケーキ屋」像が構築されていった。
父はケーキ職人になるときに「神戸の職人さんに教えてもらった」と言っていた。そこで、僕も「神戸で勉強すればいいのだな」と単純に考えて、専門学校を卒業すると「ハイジ」という神戸のケーキ屋に就職した。そこで十六年間働いて、独立し、三年後に自分の店を出した。
僕自身がこれまでケーキ職人を続けてこられたのは、ケーキづくりが上手だからではない。ケーキ屋の仕事とは、ケーキをつくることだけではないと考えていたから続けられたのだ。理由はそれだけ。
「好きなことを仕事にすると、嫌いになったときに仕事ができなくなってしまう」という言い方もあるけれど、僕には疑問だ。仮に、大好きな何かが嫌いになったとしても、自分の仕事は「そのこと」だけではないはずだ。ケーキが嫌いになったとしても、チョコレートづくりもあるだろう。パッケージデザインを考える仕事もあるだろう。宣伝する役割だってケーキ屋の仕事のなかにある。
どんなお菓子をつくるか、そのお菓子にどんなコンセプトを込めるのか、どんなパッケージに包むのか、どんな店舗で販売するのか、どんな人材を育てていくのか、といったことを真剣に考えていくと、不思議なことに自分が子どもの頃から夢中になっていたことやワクワクしたものやおいしかった感覚が活かされていくのを実感するようになった。と同時に、「自分はいったい何屋なんだ?」という自問自答も始まった。
間違いなくケーキ屋でケーキ職人なのだが、「ケーキ屋です」と一言で言ってしまうと、何かがこぼれ落ちる感覚がある。世間的にはそんな肩書きはないのだが、「ケーキを中心としたいろんなことをつなげていく人」と呼ぶのが、僕自身はぴったりする。
それは別の言い方をすると、自分の培ってきたクオリティを発揮する場面がいくつも存在する、ということになる。子どもの頃から野山で走り回って遊んで知った昆虫や草木、その感触やにおい。自分が知ったことを伝えると驚いたり喜んだりしてくれた友人や大人たちの表情。そうしたものがないまぜとなって僕の中に仕舞い込まれている。それを何かに表現したいのだ。それが、ケーキの場合もあるし、パッケージの場合もあるし、空間づくりの場合もあるし、スタッフに語る言葉になる場合もある。そうすると、必然的にいろいろなことがつながって捉えられる俯瞰的な視点になっていく。それが「ケーキを中心としたいろんなことをつなげていく人」という意味だ。
子どもの頃からの性格なのだが、きっちりとやらなければ気が済まないし、スピード感をもってやりたがる。例えば、日報もそうだ。「ハイジ」にいた十六年間、日報は一日たりとも欠かさなかった。それも、改良に改良を重ねて、自分の仕事のことだけでなく、部下の仕事のこと、チーム全体のこと、お客様のこと、会社全体のこと、将来のこと、などを一枚の中に表現することを常に意識した。誰が見ても共有できる情報やメッセージでなければ日報の意味がない、というのが自分の基準としてあったからだ。
そう考えると、「競争」というものは、本来は自分の納得できるレベルとの闘いでしかない。むしろ、それだからむずかしいのだが。しかし、自分基準での成長を目指す以外に、心からの納得は得られない。
実は、次男が僕のこの性格を受け継いだようなのだ。「もっといいものを目指す」「もっと早くやりたい」と口癖のように言っている。妻は、「そんな考えでいると他の人に嫌われてしまう」と心配しているが、そうであっても嫌われない術を身につけるのが次男の課題だと思いながら僕は見ている。
僕は、お店づくりは、スタッフの自慢話づくりでもあると考えている。
「私の働いているお店はね」と堂々と他人に語れる自慢話がいくつもなければ、仕事に対する自信も生まれない。
うちのスタッフを見て、「どういう人材育成をやられているのですか?」と尋ねられるときがあるが、僕には特別な育成能力はない。彼ら、彼女らに常にエールを送ると同時に、自分の店のことを堂々と自慢したくなる店にするには、どうしたらいいかだけを考えている。
ただ、考えれば考えるほど、やることはたくさん出てくる。自分が常に向上心を持っていないといけない。ブランド自体が薄っぺらなものにならない工夫を重ねていかなければならない。そう思わされるのは、彼ら、彼女らの存在があるからだ。
面白いことに、自慢話は、お客様の間でも連鎖として起こってくる。まるで自分が「小山ロール」を焼いたかのようにお友達に贈ったり、自分がお店をつくったかのように見てきたことを語りたくなるようなのだ。ケーキの周辺に、たくさんの人の得意げな気分が生まれたり、ワクワクしながらその話に耳を傾ける人が生まれてくるのは、この上なく嬉しい。その新鮮な臨場感が兵庫県三田(さん だ)市の小さなお店からもっともっと広がってくれるよう、自分レベルを上げ続けていきたいと思う。
その意味で、「エスコヤマ」は生き物だ。無限にかたちを変えていける生き物だ。僕は十五年間で、「エスコヤマ」のそんな変幻自在な可能性に出逢ってきたのかもしれない。
月刊『YO-RO-ZU よろず』
ご購入をご希望の方は コチラ に
1.お名前、2.ご住所 3.電話番号 と
本文内に「 月刊よろず購入希望 」と
ご記入のうえご連絡ください。